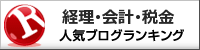インボイス制度では、商品の購入をしたりサービスを受けた場合には、適格請求書の保存が必要となっています。
しかし、少額なものまで適格請求書の保存をするのは、事務負担が大きくなります。
そこで、一定規模以下の事業者については、少額なものについては、適格請求書の保存が不要とする軽減措置が設けられました。
今回は、この一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要(いわゆる「少額特例」)について説明しましょう。
目次
少額特例の対象者|インボイス制度
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)の対象者は、・基準期間における課税売上高が1億円以下
又は
・特定期間における課税売上高が5千万円以下
の事業者です。
なお、「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいますので、当年・当期の課税売上高が1億円を超えても、基準期間の課税売上高が1億円以下であれば対象になります。
また、「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
なお、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
少額特例の対象期間|インボイス制度
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)は、適用期間が決まっています。ずっと適用になる訳ではありません。この軽減措置の対象期間は、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象になっています。
したがって、たとえ課税期間の途中であっても令和11年(2029年)10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。
少額特例の取引対象|インボイス制度
金額の判定
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)の対象になる取引は、税込1万円未満の課税仕入れです。税抜経理していても、税込金額で判定します。判定単位
また、「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、判定単位に注意が必要です。一回の取引の税込金額が1万円未満かどうかで判定します。
そのため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
これらは、減価償却資産の判定方法とは金額の判定も判定単位も異なりますね。
一回の取引ごとに判定する理由は、基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるためです。
具体例
| No. | 取引例 | 判定 |
| 例1 | 5,000円の商品をXX月3日に、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれ別で請求・精算 | 対象 |
| 例2 | 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入 | 対象外 (1万円以上の取引) |
| 例3 | 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日) | 対象外 (1万円以上の取引) |
帳簿へ所定事項の記載が条件
通常の記載事項
帳簿への通常の記載事項は次のとおりです。・相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・金額(支払対価の額)
特に、「相手方の氏名又は名称」「取引内容」の記載を忘れないようにしましょう。
帳簿に「少額特例」の記載は不要
ほかの特例では、通常の記載事項に加えて、特例の適用を受けた旨の記載が帳簿に必要ですが、この少額特例では「少額特例」などと特例を受ける旨の記載は必須ではありません。ただし、少額特例の適用を受けた旨を明確にするために「少額特例」と記載することをおすすめします。
まとめ
今回は、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要(いわゆる「少額特例」)について説明しました。この軽減措置の対象者、金額の判定、判定単位について、この記事で確認して、適用に誤りがないようにしましょう。
【消費税インボイス制度関連記事】
請求書の書き方、記載事項、変更箇所、違い|インボイス制度
請求書消費税額の端数処理|インボイス制度
請求書を修正した場合|インボイス制度
仕入れ明細書等による対応|インボイス制度
値引きや返品を行った場合の対応|インボイス制度
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)|インボイス制度
インボイス保存が不要!公共交通機関特例|インボイス制度
インボイス保存が不要!出張旅費特例|インボイス制度
3万円未満の自動販売機特例|インボイス制度
やむなくインボイス登録した事業者には「2割特例」の適用あり|インボイス制度
振込手数料の対応|インボイス制度
振込手数料(売手負担)の対応|インボイス制度
インボイス登録をやめる・取消す・取り下げる方法・手続き(2023年9月30日までに)
家賃、駐車場第等のインボイス制度対応|注意すべきポイントと手続き
タクシー代のインボイス対応には注意が必要です|イスボイス制度
ETC料金・通行料のインボイス対応(9/15柔軟対応追加)|インボイス制度
【投稿者:税理士 米津晋次】