
新聞等で年3回地価が発表されます。
じつは、公表される地価にも4種類があります。
基準地価、公示価格、路線価2種類です。
これだけ地価があると、混乱してしまいます。
毎年7月1日に公表されるのは、国税庁の路線価です。
そこで今回は、そのうち路線価(相続税、国税庁)について説明します。
目次
公表地価は4つ|(3)路線価(相続税)とは
路線価(相続税)を決めるのは、国税局長
路線価(相続税)は、国税局長が相続税や贈与税を計算する際の土地を評価する基準となるものとして、市街地的形態を形成する地域の道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの評価額を定めたものです。基準がないと、相続税や贈与税の負担が不公平になってしまいますので、路線価という基準が設けられているのです。
なお、日本全国のすべての道路に路線価がついている訳ではなく、市街地以外は路線価はついていません。
路線価は、主に市街地の土地を評価するのに使用され、路線価が無い地域は、別の方法で土地が評価されます。
路線価(相続税)は、7月に発表される
相続税の路線価は、国税庁によって毎年7月に、その年の1月1日時点の価格が公表されています。相続税の申告期限は、亡くなってから10ヵ月です。1月に亡くなった方の相続税の計算をするには、7月に発表しないと間に合わないということで、7月発表になっているのでしょう。
相続税の路線価は、国税庁ホームページで参照できる(見方)
相続税の路線価を知りたいときは、税務署へ聞きにいくしかないのでしょうか。いえ、国税庁ホームページから誰でも簡単に調べることができます。
国税庁ホームページから「路線価図」のバナーをクリックします。日本地図が表示されますので、参照した地域を都道府県から選択していきます。
すると、たとえば次の図のように、各道路に数字がついた図が表示されます。その数字がその道路に面する土地の1㎡あたりの基準となる価格です。(表示は千円単位)

たとえば、上図では、浅草花やしきの北側の道路には「320」という数字がついています。
これは、その道路に面する土地の評価額は、1㎡当たり32万円が基準になるということになります。
なお、数字の後ろのアルファベットは、借地権割合を表しています。「C」であれば、借地権割合が70%であることを表しています。
→ 国税庁路線価
各土地の評価額は、路線価から補正する
路線価図では、同じ道路に面する土地ならすべて同じ価格になる訳ですが、当然各土地の価格は同じではありません。実際には、土地の形状や間口の長さ、奥行き、整地が必要かどうかなど、それぞれの土地の状況に応じて、路線価から補正をしていきます。
公表地価は4つ|(3)路線価(相続税)は相場の8割(80%)程度
相続税路線価が公示価格(実勢価格、時価)の8割(80%)程度の理由
相続税の路線価は、公示価格(時価)の8割(80%)程度になっています。それはなぜなのでしょうか?それは、路線価による土地の評価が実際の時価を上回ることの無いように安全性を考慮して定めているからです。
公示価格や基準地価は、あくまでその土地価格の目安であって、その土地が必ずその価格で取引される訳ではないのです。
実際に土地の価格は、売り手と買い手の合意によって決まるのですから、いくら公示価格が○○円です、といっても、さまざまな事情で取引価格は公示価格から高くなったり安くなったりします。
また、公示価格は1月1日時点の価格であり、相続や贈与の日がたとえば12月だとすると、1年近いずれが生じていて、その間に土地の価格が上昇したり下降したりするのが普通です。
つまり、その土地の本当の価格(時価)はわからないのが正解です。
相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額が、もし本当の時価よりも高くなると、適正な相続税や贈与税よりも過剰な負担を納税者にさせることになり問題です。
そこで、相続税や贈与税の計算で算出する土地の評価額が実際の価格を超えることのないように、路線価は公示価格の8割(80%)程度により評価しているのです。
なお、それでも稀に相続税法による評価額が実際よりも高くなることがあります。
そのような場合には、不動産鑑定士による評価額によって申告することができます。
相続税路線価から時価が推定できる良さもある
公示価格や基準地価は、確かにほぼ時価を表していますが、その価格がついているのは基準値に限られます。つまり、すべての土地について価格がついている訳ではありません。むしろ、ほんの一部の土地にしかついていないといえませ。
そうすると、たとえば購入したい土地の価格を推定するのに、公示価格や基準地価の基準地と距離がありすぎると、目安の価格もなかなか算出できません。
それに対し、相続税の路線価は、市街地であれば、ほぼすべての道路に価格がついていますので、目的とする土地の路線価もすぐわかります。
路線価は公示価格の80%程度とされていますので、路線価を80%で割り算して逆算すれば、公示価格が推定できます。
したがって、路線価から取引価格を推定するには、
・路線価÷80%
で算出することができます。
公表地価は4つ|(3)路線価(相続税)と路線価(固定資産税)との違い
路線価には、相続税の路線価と固定資産税の路線価の2種類があります。相続税の路線価と固定資産税の路線価との違いについてまとめてみます。
路線価を使用する税金が異なる
相続税の路線価は、相続税や贈与税を計算する際に使用します。それに対し、固定資産税の路線価は、固定資産税を計算するのに使用します。
相続税の路線価を決めるのは国で固定資産税は市町村
相続税や贈与税は国税ですので、相続税の路線価は国が決定します。それに対し、固定資産税は、市町村税ですので、固定資産税の路線価は市町村(市長など)が決めることになります。
各路線価の公示価格に対する割合
相続税の路線価は、公示価格の8割(80%)程度になるように決められていることは説明しましたね一方、固定資産税の路線価は、公示価格の7割(70%)程度になるように決められています。
まとめ
4種類ある公表される地価のうち、今回は、相続税の路線価について説明しました。今回はどの地価が発表されたのか、そしてそれはどのようなものかをしっかり理解していただきたき、その地価を有効に活用していただきたいと思います。
・公表地価は4つ|(1)基準地価とは、目的、発表日、公示価格との違い
・公表地価は4つ|(2)公示価格とは、目的、発表日、基準地価との違い
・公表地価は4つ|(4)路線価(固定資産税)とは、目的、発表日、相続税路線価との違い

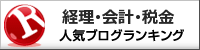























































コメント
コメントはありません。