
出産にはとても金がかかりますね。出産は通常健康保険がききません。
健診や出産費用などで50万円~100万円程度のお金がかかります。
このようなときに、少しでも負担を軽減できるのが、医療費控除制度です。
そこで今回は、出産の場合の医療費控除について説明します。
目次
出産の医療費控除|出産関係で医療費控除の対象なるものは?
まず、出産関係で医療費控除の対象なるものについて説明していきます。分娩費
出産費用や助産師による分娩の介助料は、もちろん医療費控除の対象になります。
帝王切開の場合
安全に出産するために帝王切開が選択されるケースもあります。帝王切開は、通常の出産費用と違って、健康保険が適用されます。しかし、いくら健康保険が使えるといっても、帝王切開は通常分娩と比較して入院期間が長くなることが多いですから、結果として出産費用が通常の出産より多くかかります。
このような帝王切開費用も、もちろん医療費控除の対象になります。
参加医療補償費
病院によっては、産科医療補償制度に加入していることがあり、分娩費のほかに、産科医療補償費を支払うこともあります。この産科医療補償制度は、出産した赤ちゃんに重度の脳性麻痺が発生した一定の場合に補償される制度だそうです。
この病院に通常の分娩費に上乗せして支払う産科医療補償費は、分娩費の一部という考え方で、医療費控除の対象になります。
なお、健康保険組合から支払われる出産育児一時金の金額は、この産科医療補償費が上乗せされて支給されますので、自己負担にはなりません。
また、医療費からも控除しますので、医療費控除額も結果的に変わりません。
出産までの検診代
出産までの検診代は、通常は治療ではありませんので医療費控除の対象にはなりませんが、妊娠中の定期検診費用は、例外的に医療費控除の対象になります。妊娠しているということは、すでに通常の健康体ではないと考えられるからです。
 → 妊婦の定期検診のための費用(国税庁)
→ 妊婦の定期検診のための費用(国税庁)出産のタクシー代
また、交通費は公共交通機関を利用したものが医療費控除の対象になりますので、タクシー代は通常医療費控除の対象から外れます。しかし、妊娠してつわりがひどい場合やお腹が大きくなってきた場合などは、電車やバスでの移動が困難と認められますので、タクシー代も医療費控除の対象として認められます。

出産入院の食事代
出産のための入院で支払う食事代については、部屋代と一緒に病院に支払うものは、原則医療費控除の対象になります。この扱いは、出産入院に限らず、病気入院の場合も同じです。
したがって、病院の食事が気に入らないから出前をとった場合の食事代や外食は、医療費控除の対象にはなりません。
また、最近はフランス料理などの豪華な食事が出る産婦人科もあるようです。常識の範囲を超えた豪華な食事代も医療費控除の対象にはなりません。

なお、付き添いした家族の食事代は、医療費控除の対象になりません。
→ 入院患者の食事代(国税庁)
→ 親族が付き添う場合のその親族の食事代(国税庁)
出産入院で着た寝巻き等
出産入院中に着る寝巻きや洗面道具、テレビのレンタル代などは、出産に直接費用なものではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。これは、出産以外で入院の場合と同じ扱いですね。

一方、医師の指示で購入したガーゼ代や脱脂綿代は、医療費控除の対象になります。
→ 入院のための寝具や洗面具等の購入費用(国税庁)
→ 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等(国税庁)
出産時に頼んだ子供の世話代
2人めの出産であれば、最初のお子さんのお世話を誰かに頼まなければならないことも多いかと思います。しかし、その世話代は、そのお子さんの世話という家事上のものです。
したがって、家政婦さんに支払った世話代は、医療費控除の対象にはなりません。
また、お母さんを子供の世話のために呼んだ場合の交通費や生活費も、医療費控除の対象にはなりません。
実家で出産するために帰省するための旅費
実家で出産するために帰省する場合もありますが、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。残念ながら、実家へ帰省する旅費については、医療費控除の対象とはなりません。
→ お産のために実家へ帰る旅費(国税庁)
出生前遺伝学的検査費用
妊婦から採血することにより行われる出生前遺伝学的検査は、医療費控除の対象にはなりません。この出生前遺伝学的検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるもので治療ではなく診断の一種です。
また、出生前遺伝学的検査の結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながらないとされているからです。
→ 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用(国税庁)
無痛分娩講座受講料
無痛分娩講座を受け、腹式呼吸などの指導を受ける際に支払った受講料は、医療費控除の対象とはなりません。医師による診療費ではないためです。
→ 無痛分べん講座の受講費用(国税庁)
出産費の医療費控除可否まとめ
以上説明してきた出産費の医療費控除可否をまとめてみます。| 出産費の内容 | 医療費控除対象? |
| 分娩費 | ○ |
| 帝王切開費 | ○ |
| 参加医療補償費 | ○ |
| 出産の検診代 | ○ |
| 出産時のタクシー代 | ×(電車やバスでの移動が困難な場合は○) |
| 入院食事代 | ○(出前、外食、豪華なものを除く) |
| 入院時の寝巻き、洗面道具 | × |
| テレビレンタル料 | × |
| 子供の世話代 | × |
| 実家でお産するための旅費 | × |
| 出生前遺伝学的検査費用 | × |
| 無痛分娩講座受講料 | × |
出産の医療費控除|出産手当、出産一時金は控除する?
医療費控除で医療費から引くべきもの
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。・実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額
なお、この「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費などです。
したがって、これらに該当する場合の医療費控除の計算において、医療費から差し引く必要があります。
医療費控除で出産手当は医療費から引く?
出産手当とは
健康保険に加入している本人が出産のため会社を休み、産前42日、産後56日の産休中に給与の支給がされない場合は、産休中の生活をサポートするために勤務先の健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の1日あたりの支給額は、次のとおりです。
・支給開始日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)
なお、出産手当金は、通常は産休が終わった時点での申請になるため、産後57日以降に勤務先や年金事務所に提出します。
また、出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。
ただし、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
出産手当金は医療費控除で差し引く必要はない
健康保険からの出産手当金は、「保険金などで補てんされる金額」に含まれません。出産手当金は、産休中の生活をサポートするのが目的であって、出産費用などを補うものではないからです。したがって、出産手当金は、医療費控除の医療費から差し引く必要はありません。
→ 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(注意事項)(国税庁)
医療費控除で出産一時金手は医療費から引く?
出産一時金(出産育児一時金)とは
健康保険に加入している本人または扶養家族で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合には、健康保険の種類に関係なく、妊娠・出産に必要な費用をサポートするため、「出産一時金」が支給されます。被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」といいます。
出産一時金の支給額は、1児につき42万円です。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円となります。)
加入している健康保険組合や国民健康保険に支給を申請すると受け取ることができます。
出産一時金は、医療費控除の医療費から控除する
出産一時金は、「保険金などで補てんされる金額」に含まれます。したがって、出産手当一時金は、医療費控除の医療費から差し引く必要があります。
→ 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(注意事項)(国税庁)
出産の医療費控除|出産費用等が年をまたいだ場合は?
出産のための入院と退院の間で年が変わる場合もあります。そのような場合の医療費控除は、どのようにするのでしょうか。
医療費控除はいつ支払ったかで判定する
医療費控除は「いつ支払ったか」により、どの年の医療費控除の対象になるかが決まります。出産費用も同じです。いつの分かで判断するのではありません。
したがって、12月31日までに支払った分と、1月1日以降に支払った分を分けて、それぞれの年の医療費控除をします。
ただし、年末までに予約金を支払った場合で年をまたいで退院した場合は、予約金の支払いが前年であっても、退院日である翌年の医療費控除の対象になります。
出産一時金や保険の給付金の支給が年をまたいだ場合
出産・退院は年内で、出産費用も年内に支払ったものの、出産一時金や保険の給付金の支給が翌年になった場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は、入金日で判断するのではなく、出産費用との対応関係で判断します。
したがって、入金が翌年にずれこんだとしても、医療費控除の申告では、対応する出産費用を医療費控除申請する際に、出産費用から控除することになるのです。
出産の医療費控除|共働きの場合どちらから控除すると有利か?
医療費控除は所得控除
確認ですが、医療費控除は所得控除でしたね。課税対象所得金額を計算する前で引くものです。医療費控除額による税金の還付額は、所得税率が累進税率となっているため、所得によって異なります。

所得の高い方で医療費控除するのが有利
所得の高い人は税率が高いため、同じ医療費でも、所得の低い人より所得税の還付額が多くなります。【事例】医療費(出産費用を含む)が30万円の場合
| 区分 | 還付額 |
| 平均税率10%の人 | (30万円-10万円)×10%=2万円 |
| 平均税率30%の人 | (30万円-10万円)×30%=6万円 |
不妊治療費、妊娠中絶費用の医療費控除
不妊治療や人工授精費用は医療費控除の対象になるか?
医師による診療等で支払った不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になります。→ 不妊症の治療費・人工授精の費用(国税庁)
【詳細】 → 医療費控除|不妊治療費は対象になる?
妊娠中絶費用は医療費控除の対象になるか?
妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶費用は、医療費控除の対象となります。→ 妊娠中絶の費用(国税庁)
医療費控除の概要
医療費控除とは?
家族の医療費を、原則として年間10万円を超えて支払った場合には、10万円を超えた部分について所得税・住民税の対象となる所得から引くことができます。(最高200万円)これを医療費控除といいます。
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%の金額を超えた部分について、医療費控除を受けることができます。
医療費控除で所得税・住民税はどれだけやすくなる?
医療費控除を受けると、次の所得税・住民税が安くなります。1箇所のみに勤務するサラリーマンの場合は、すでに所得税が源泉徴収(控除)されていますので、所得税については還付を受けることになります。
・年間支払った医療費のうち、原則として10万円を超える金額×所得税率・住民税率
所得税率は、所得金額に応じて5%~%です。(特別復興所得税を除く)
また、住民税率は、一律10%です。
【具体例】
年間支払医療費:20万円、所得税率5%の場合
・所得税:(年間支払医療費20万円-10万円)×5%=5,000円
・住民税:(年間支払医療費20万円-10万円)×10%=10,000円
・合計 :5,000円+10,000円=15,000円
(復興税は省略しています)
ただし、医療費控除で控除される金額は、課税所得金額が限度となりますので、たとえば、源泉徴収された所得税額が0円の場合、所得税の還付はありません。
医療費控除で対象となる医療費とは?
医療費控除の対象となるのは、主に治療が目的のものに限られます。具体的には、主に次のものです。
入院費・通院費など
・医師等に支払った診療費・治療費・治療のための松葉杖・義足の購入費用
・入院時に提供される食事代
・通院や入院のための交通費
・レーシック手術
・治療としての歯列矯正
医薬品
・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品・病気やケガの治療のために、薬局で購入した医薬品
医療費控除を受ける手続き
医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄の税務署長に提出する必要があります。また、医療費の明細書を作成して確定申告書に添付しなくてはなりません。領収書の提出は不要になりました。(ただし、5年間の保存が必要です。)
なお、給与所得のある人の「給与所得の源泉徴収票」の添付は不要になりました。

→ 確定申告の医療費控除|条件、医療費に該当する?還付額は?やり方
まとめ
出産に関する医療費控除について説明してきました。医療費控除について、「知らなかった」とか、「確定申告するのを忘れてしまった」などの場合も、5年間は遡って医療費控除の申請ができますのでご安心下さい。
確定申告の際には、出産手当金と出産一時金の医療費控除での違いに注意してください。
【医療費控除関係記事】
・医療費控除の確定申告|いくらから、医療費に該当する?還付額は?やり方
・医療費控除の領収書はどうするの?(提出・保管は必要?紛失の場合など)
・「医療費のお知らせ」を利用した医療費控除のやり方・注意点
・医療費控除入院費|食事代・おむつ代・差額ベッド代は対象?保険金は?
・医療費控除|薬局で購入した薬代(風邪薬・絆創膏など)は対象になるのか
・医療費控除で人間ドック費用は対象か?精密検査・再検査・PET費用は?
・出産の医療費控除のポイント|検診・タクシー代、出産手当・出産一時金
・医療費控除|不妊治療費は対象になる?助成金は?高額交通費は?
・歯科の自由診療(自費診療、保険外)は対象になるのか?
・医療費控除で歯科矯正は対象?(子供の場合、大人の場合、書き方)
・医療費控除|介護保険居宅・施設サービス、介護ベッド・用品代、レンタル等で対象になるもの
・補聴器も医療費控除できる?その条件や手続き・方法は?
・セルフメディケーション税制(新医療費控除)って何?|概要、対象薬品、申請方法・申告方法など
【参考動画】(国税庁)
→ 医療費控除の入力方法
【投稿者:税理士 米津晋次】

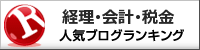





















































コメント
コメントはありません。