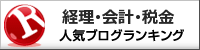所得税の確定申告の申告内容は、あくまで自己責任です。
とはいっても、人間ですから確定申告でうっかり申告を忘れやすいものがあります。
そこで今回は、申告書を提出する前に最終チェックしていただきたい漏れやすい・忘れやすい項目をあげてみます。
確定申告書の提出前に確認してください。もちろん提出後でもOKです。
目次
- 1 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|生命保険満期金など
- 2 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|所得税還付加算金
- 3 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|医療費控除補てん金
- 4 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|ふるさと納税ワンストップ特例
- 5 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|寡婦控除、ひとり親控除
- 6 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|国外所得
- 7 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|予定納税額
- 8 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|所得拡大促進税制
- 9 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|為替差益
- 10 確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|仮想通貨
- 11 まとめ
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|生命保険満期金など
満期保険金・保険解約返戻金は一時所得
自分で保険料を負担していた生命保険や損害保険について、生命保険会社などから満期保険金や一時金を受け取った場合、保険を解約した際に返戻金を受け取った場合は、一時所得として申告する必要がある場合があります。特に、農協の建物更生保険(建更)の満期金は忘れやすいと思います。
このような保険満期金などがなかったか、もう一度確定しましょう。

満期保険金などの一時所得の計算
・一時所得の金額=満期保険金など-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)「収入を得るために支出した金額」は、生命保険会社などから送付されてくる「満期保険金振込のお知らせ」などに記載されています。
ただ、「特別控除」がありますので、その年の一時所得金額合計が50万円以内なら、申告し忘れても問題ありません。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|所得税還付加算金
前回の確定申告で所得税が還付になった場合は要注意
前回の確定申告で所得税が還付になった場合には、「還付加算金」といって、利息相当額が加算された金額を受け取っている場合があります。たとえば、所得税還付金が10万円の場合、実際には、所得税還付加算金2000円が加算されて、102,000円が口座に入金されたとします。
確定申告する場合には、この「所得税還付加算金」も申告しなければなりません。
これは、税理士事務所でも、ついうっかり忘れる代表的なものです。

所得税還付加算金は雑所得
たとえ、事業所得に関係する所得税還付金を受け取った際に加算された還付加算金であっても、所得税還付加算金は、事業所得ではなく、雑所得になります。還付加算金には、必要経費に該当するものがありませんので、還付加算金がそのまま雑所得金額となります。
この「所得税還付加算金」は、還付する税務署側で当然管理していますから、もし確定申告で計上し忘れた場合には、税務署から連絡が来て、修正申告することになる可能性が高いです。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|医療費控除補てん金
医療費控除額の計算
とても認知度が高い医療費控除ですが、医療費控除額は、次のように計算します。・ (実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)※最高20万円
(1) 給付金や高額療養費などで補填される金額
(2) 10万円。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%の金額です。
負担した医療費を忘れることはないかと思いますが、上記の「給付金や高額療養費などで補填される金額」を引くのを忘れやすいのです。
給付金や高額療養費などで補填される金額の例
医療費控除額の計算で差引く「保険金などで補填される金額」には、次のようなものがあります。・高額療養費
・高額介護合算療養費
・出産育児一時金
・生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金
など
これらを受け取った場合には、医療費控除額の計算で、忘れずに控除するようにしましょう。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|ふるさと納税ワンストップ特例
ワンストップ特例は、確定申告を省略できる制度
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは、確定申告が不要なサラリーマンなどでふるさと納税を行った場合でも、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。適用を受けるためには、寄附した自治体ごとに申請書を提出しなければなりません。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請しても確定申告で申告が必要
ふるさと納税で確定申告がいらないという「ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している人でも、確定申告をする場合には、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めなければなりません。ワンストップ特例は、確定申告不要な人のための制度だからです。
確定申告でふるさと納税を申告すると、まず所得税から控除し、残りを住民税から控除することになります。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|寡婦控除、ひとり親控除
寡婦・寡夫控除やひとり親も、確定申告で忘れやすい項目のひとつです。
寡婦とは
寡婦とは、自分(納税者)が、原則としてその年の12月31日の現況で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人のことをいいます。(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後、婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
→ 寡婦控除(国税庁)
ひとり親とは
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。男性でも受けることができます。(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
→ ひとり親控除(国税庁)
寡婦・ひとり親控除は自分で申告する
自分が「寡婦」や「ひとり親」に該当し、寡婦控除やひとり親控除の適用を受けられるかどうかは、自分しかわかりません。判定の内容は、かなりプライベートなことになりますので、なかなか他人からは質問しづらいものです。
したがって、「寡婦」「ひとり親」に該当するかどうかは、自分で判定するようにしましょう。
そして、もし「寡婦」「ひとり親」に該当する場合には、忘れずに申告して所得控除をうけましょう。
税務署は「寡婦」や「ひとり親」に該当するのに適用を忘れた場合でも、親切に「忘れていますよ」なんて言ってくれませんから。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|国外所得
原則として世界での所得が日本の確定申告の対象
簡単に言えば、日本人なら、日本における所得だけでなく、外国のどこの国における所得であっても、確定申告で申告しなければなりません。たとえば、外国株式や海外ETF、外国債権の利子や配当などが国外所得に該当します。
所得税の確定申告といえば、どうしても日本での所得のことだけを考えがちです。外国での所得も忘れずに申告しましょう。

国外所得は外国税額控除で二重税金を解消
国外所得のうち、外国株式や海外ETF、外国債権の利子や配当などは、海外で税金がかかります。そして、日本では外国の所得も申告しますから、所得税がかかることになります。
海外での税金と日本の所得税と二重の税金がかかることになります。それではおかしいですね。
そこで「外国税額控除」を受けることによって、二重の税金にならないようにできます。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|予定納税額
所得税の予定納税額とは
個人事業者などは、確定申告で確定した年間の所得税を翌年3月15日までに一括して納める訳ではありません。前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上である場合には、その年の所得税等の一部を前払いして納付する制度があります。
この制度を予定納税といい、予定納税で納付する所得税額を予定納税額をいいます。
所得税の予定納税は7月と11月
この所得税の予定納税は、前年税額の1/3ずつを7月末と11月に納付します。
よく忘れる所得税予定納税額の記入
この所得税の予定納税額の記入が忘れやすいのです。所得税の計算ができた!と思ってホッとしてしまいます。税理士でもよく忘れる項目の一つです。
予定納税額を知るには
予定納税を口座振替で行っていれば、通帳を見れば予定納税額はわかります。現金で納付した場合は、納付書の控えで確認しましょう。
電子申告をした方は、1月にメッセージボックスに配信される「申告のお知らせ」の中に、予定納税額の記載があります。
どうしてもわからない場合は、身分証明書を持って税務署の窓口へ行きましょう。教えてくれるでしょう。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|所得拡大促進税制
賃上げ促進税制とは
政府は賃上げを奨励していますね。それに応えて賃上げをして一定の要件を満たした個人事業主には、所得税を最大20%減額(税額控除)するという制度です。
法人だけに適用されているように思うかもしれませんが、青色申告をする個人事業主もその対象者です。
前年と比較して給料が増えていれば、賃上げ促進税制が受けられるかも
この賃上げ促進税制は、税務署から、あなたは所得拡大税制の対象ですよ、なんて教えてくれません。自分で申告しない限り適用されることはないのです。
税理士でもうっかり忘れやすいものの一つです。
適用対象かどうかは、細かい条件があるのですが、まずは給料をここ数年比較しましょう。
増えているようであれば所得拡大税制を受けられるかもしれません。

賃上げ促進税制の詳細は、次の資料をご覧ください。
→ 賃上げ促進税制(国税庁)
適用条件に該当するのであれば、忘れずに申告しましょう。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|為替差益
外貨預金の為替差益は雑所得
外貨預金をやっている方はみえませんか?円預金はあまりにも金利が低いので、金利が円預金よりも高いドル預金などの外貨預金が人気になっています。
外貨預金は、利息だけでなく、預入れ時の為替相場よりも円安になると得するしくみですね。
つまり、為替差益です。
外貨預金による為替差益であっても、それが少額であっても、それは雑所得となります。

確定申告の際には、少額の為替差益も申告しなければならない
為替差益が少額であれば、サラリーマンの場合には、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要を選択することができます。しかし、サラリーマンでも、医療費控除や住宅ローン控除をするために確定申告する場合には、為替差益を少額でも必ず申告しなくてはなりません。
サラリーマン以外の方は、20万円以下申告不要の特例はありませんから、為替差益を含めて所得合計が48万円を超える場合には、確定申告をする義務があり、当然そこには為替差益による雑所得も申告しなければなりません。
為替差益の雑所得の計算
為替差益は、必要経費というものがありませんので、為替差益がそのまま雑所得金額となります。ただし、ほかの外貨預金などで為替差損がある場合には、為替差益と為替差損は相殺(損益通算)をすることができます。
たとえば、A外貨預金で為替差益が10万円出ても、B外貨預金で為替差損が3万円あった場合には、10万円-3万円=7万円が雑所得となります。
確定申告で漏れやすい・忘れやすいもの10選|仮想通貨
仮想通貨を円に換えなくても所得が発生する場合がある
仮想通貨を売って円に換えた際、売却益が出れば、雑所得として確定申告の義務がありますね。これは仮想通貨取引をしている方ならわかると思います。
ところが、仮想通貨を売却していなくても、雑所得が発生する場合があるのです。
それはどのような場合かというと、次の場合です。

仮想通貨で買い物をする
たとえば、ビットコインを扱っている店で買い物をし、日本円の代わりにビットコインで商品代金を支払った場合、その代金(日本円)でビットコインを売却したことになります。ビットコインを円に売却して、その円で買い物をしたと考えるからです。このように、仮想通貨を使って買い物をした場合も、仮想通貨を売却したことになり、売却益が発生すれば、雑所得となります。
A仮想通貨をB仮想通貨へ換金する
たとえば、ビットコインをリップルへ交換したように、仮想通貨同士を交換した場合も、雑所得が発生することがあります。たしかに、仮想通貨を売った訳ではありませんが、一度円へ売却し、その円で別の仮想通貨を購入したと考えるからです。
ICOに参加して、アルトコインをイーサリアムで購入した場合も、同じ扱いです。
まとめ
今回は、所得税確定申告書を提出する前に最終チェックしていただきたい漏れやすい・忘れやすい項目をあげてみました。これらは、なかなかチェックがかからないものです。
しっかりチェックしてから申告書を提出しましょう。
10選にはあげなかったのですが、最後のもう一つだけ忘れやすいものを。
中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)の掛金を必要経費にしている場合には、「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を申告書に添付することです。添付を忘れると、掛金が必要経費として認められません。ご注意を!!
→ 確定申告用紙ダウンロード
確定申告の間違いに提出後に気づく場合もあるでしょう。その場合は、次をご覧ください。
→ 確定申告各種チェックシート
また、各種特例を受けた場合には、チェックシートで適用条件や添付書類を確認しましょう。
→ 確定申告の間違いに気づいた場合はどうする?
【投稿者:税理士 米津晋次】